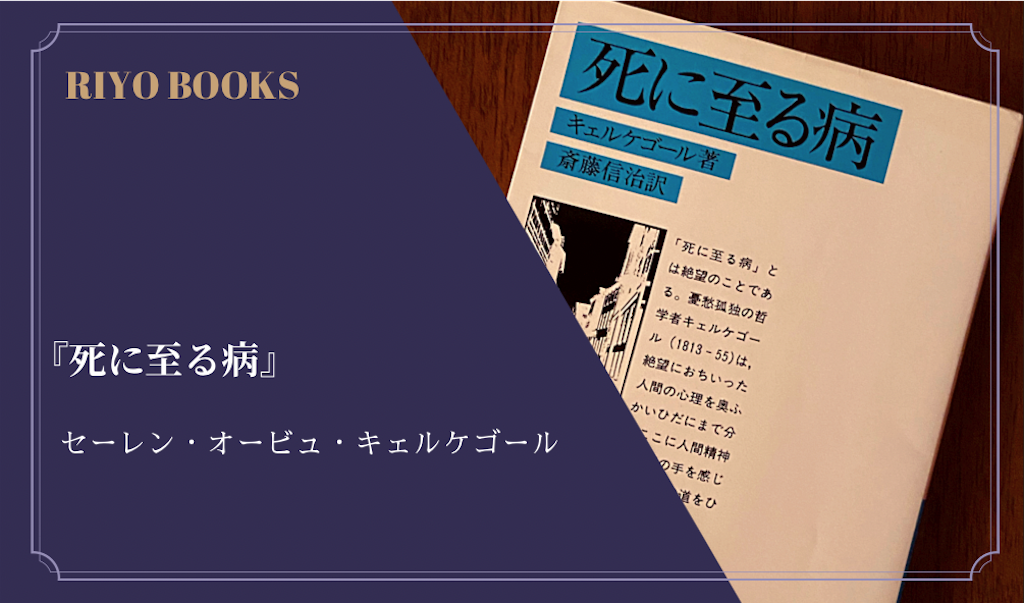
こんにちは。RIYOです。
今回はこちらの作品です。

セーレン・オービュ・キェルケゴール(1813-1855)はデンマークの思想家であり哲学者です。当時のゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルを中心とした理想主義の席巻は、宗教論にまで派生してデンマークの各教会にまで影響(ぐらつき)を与えるほどでした。これに対抗する思想を立ち上げてぶつかり合ったキェルケゴールは、現在における実存主義の先駆けとして後世に影響を与え続けています。
作品名である『死に至る病』は新約聖書「ヨハネによる福音書」から引用されています。病によって命を落とした友人ラザロをイエス・キリストが蘇らせた際、「この病は死に至らず」と発しました。この時の死因が「絶望」であったことから、本作にはこの題名が付けられました。副題は「教化と覚醒のためのキリスト教的、心理学的論述」としており、敬虔なクリスチャンの立場(アンティ=クリマクスという別名で出版)で強い信仰心の元に書かれています。
今ある自己(現自己)が受けた極限的不幸によって自己の精神は変化します。精神が現自己から遠く離れたいが現自己は自己であるために逃れられない状態、また現自己であり続けようとするが不幸の永続性に苦しみ続ける状態、また現自己からあるべき自己(本自己)へと移行したいが肉体や精神が伴わない状態、これらを総括して「絶望」と呼びます。
「絶望」は自己の在り方によって段階的に幾つかに分類されます。
無限性絶望は、自己を世間と比較して立ち位置を定めて、より高みに登ることができたなら、と希望的空想に思いを巡らせて逃避的思考へと移行し、本自己から遠ざかり続けることを言います。それは本来なすべき行為や目の前の問題を放棄することに繋がっていきます。
有自覚的絶望は、世間との自己比較によって見出された否定的差異を理解しながらもそれを受け入れて、且つ、諦めの観念を持ちながら世間との調和のみを求めて過ごすことを言います。騙り取り(かたりとり)と表現しますが、諦めや不貞腐れに近い状態で、これもやはり、なすべき行為や解決すべき問題から目を逸らしていると言えます。
可能性的絶望は、現自己を置き去りにして空想的観測に委ねて現在を見失っている状態です。置かれている状況や危機的問題に目を向けず、妄想に耽って現実から逃避していることを言います。
必然性的絶望は、本自己を見失っている状態です。あるべき、或いは、ありたいとする自己を見ることができず、ただただ目の前の現実に打ちひしがれて盲目的であり、先を見ようとする意欲が湧かず、諦めの観念に包まれています。
キェルケゴールは「絶望」を罪であるとしています。絶望の発端となる思考は、世間の目やその評価からくるものであり、対人間としての価値観から陥る否定的な精神状態です。本自己と現自己の乖離に、俯き、激昂し、諦めながらも受け入れないことは、人間の内における永続性としての精神の停滞であり、そこから快方へ向かおうとする思考の否定です。信仰対象の「神」に肯定的可能性を求め、祈り、救済を願うことを正とし、永続的な否定的精神状態からの解放を望むことこそ必要であるとしています。これを求めず、神の存在を認めていながらも、精神状態を否定的に置き続けることを罪であると唱えています。
信仰は理性の否定とも言えます。現自己の否定であり、自意識の否定であるとも言えます。しかしその上で神という存在を認め、神の持つ可能性へと望みを委ねることこそ「信じる」行為であると彼は言います。
自己自身において、現自己の置かれた否定的状況による否定的精神状態を受け入れること、本自己との乖離を認めてその距離を埋めようと望む可能性を抱くこと、そして神の前でその可能性を祈り願うこと、これらを「信仰」であるとしています。だからこそ、「信仰」の否定は「神」の否定であり、可能性を求めず絶望状態を維持継続し続けることを「罪」であると訴えています。「絶望」という病に処方すべき薬剤は「可能性」であり、それを求めずに打ちひしがれる「罪」を、神への「信仰」により振り払うことが必要なのです。
キェルケゴールは「神の前に」と何度も強調します。神は絶対的な存在であり、何ら論証も必要なく、信心の元に信仰の対象となるべき存在であると唱え続けます。神とは思弁的な対象となるものではなく、論証的に確証されてはならない、人間の思考により生まれる「知」の一部であってはならないとして、絶対的な存在であり、だからこそ人間の救いたり得ると考えています。これはヘーゲルの精神現象学における宗教論に対する姿勢です。ヘーゲルの宗教論は、宗教とは人間精神がとる一つの究極的な形であるとして、啓示を通して神が人間に、人間が神に精神を触媒として聖霊的受胎を認め、神が自己に内在するという考え方を説いたものです。この宗教論に対して、「神と人を同等に考えるとは何ごとか!」とキェルケゴールは激昂しました。ヘーゲルを無神論者であると断じた上で、本作『死に至る病』の執筆において反証的にヘーゲルの宗教論を否定します。このことが「神の前に」を頻出させる根拠となっています。そして本作においてはイエス・キリスト(神)を否定することが「絶望における可能性の否定」であることとして、永続的に絶望であり続けると述べています。
絶望における可能性への転化を「逆説」的思考と捉えて、池田晶子さんは以下のように述べています。
逆説とは思想の情熱であり、逆説をもたない思想家は情熱をもたぬ恋人、そしてすべての情熱は自身の破滅を欲する、ゆえに理性もまたその極致において。
理性には理解不能な逆説それ自体、逆説が存在するというそのこと自体が、この人にとっては「神」なのである。いや神と「言いたい」のである。神と人とはあくまでも別ものであるべきだという根強い思い込み、じつはそれこそが信仰なのだと言うべきだろう。
池田晶子『人生は愉快だ』
信仰における根拠の有無は非常に現代的な問題とも言えます。中世において無条件に神を崇めることは当然なことでした。しかし時代が進むにつれて、哲学は細分化し、精神研究も複雑化して、あらゆるものの根源に対する疑問が浮かび上がっていきます。信仰に対象が自由であれば、信仰するかどうかという、そのもの自体にさえ自由があります。
人間は誰しもが現自己と本自己に挟まれて生きています。その中で、突如として訪れる大きな苦難が絶望の切っ掛けとして口を開けて道の先で待ち受けています。自己自身が陥る絶望という病に、可能性という薬剤を自身で処方できるかどうかは、その時の信仰の有無によるのかもしれません。
現代における苦悩からの脱却の糸口ともなり得る本作『死に至る病』、随所で考えさせられる素晴らしい作品です。未読の方はぜひ、読んでみてください。
では。
