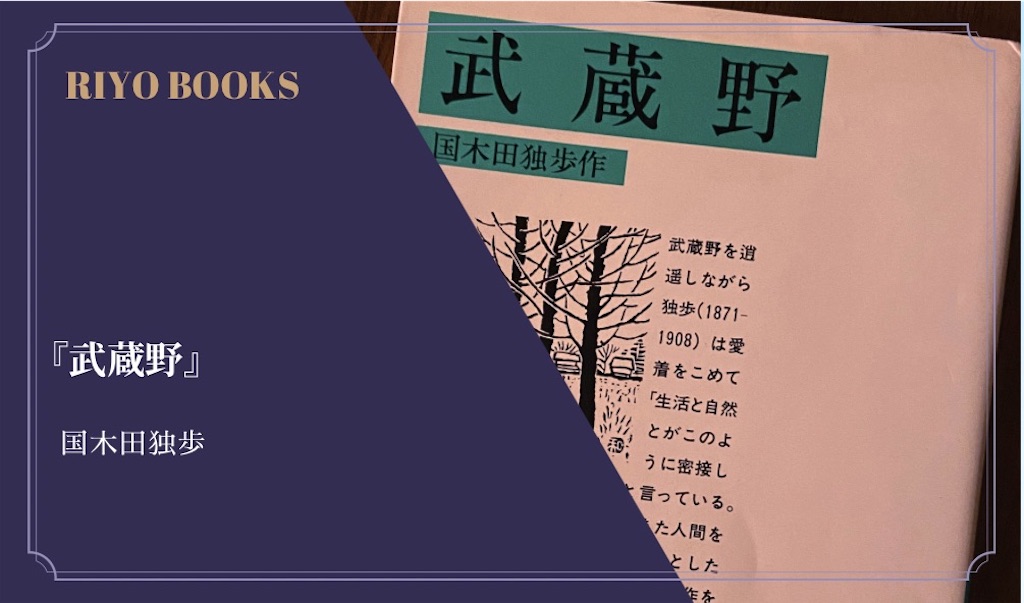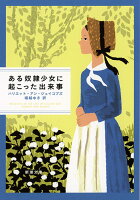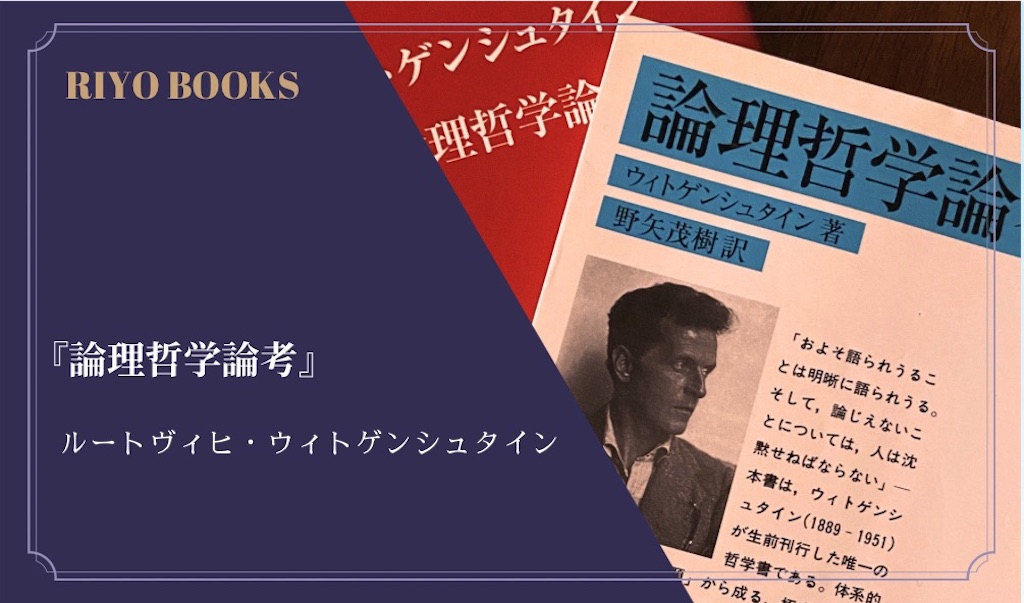
こんにちは。RIYOです。
今回はこちらの作品です。

父親のカール・ウィトゲンシュタインは一代でオーストリアにおける鉄鋼業界を牽引し、莫大な財産を築き上げました。その富と名声に加え、ウィトゲンシュタインの両親ともに音楽に造詣が深かったことから、多くの音楽家たちが邸宅に訪れるサロンのような存在となっていました。親族であるヨーゼフ・ヨアヒムは当然ながら、フェリックス・メンデルスゾーン、クララ・シューマン、ヨハネス・ブラームス、グスタフ・マーラー、ブルーノ・ワルターといった、当時のウィーン音楽界を代表する多くの音楽家たちによる演奏会が毎日のように開かれていました。また、アーツ・アンド・クラフツ運動に影響を受けた建築家ヨーゼフ・ホフマン、近代彫刻の父と呼ばれるオーギュスト・ロダン、ドイツロマン主義の詩人ハインリヒ・ハイネ、官能的ファム・ファタルを得意とした画家グスタフ・クリムトなどの芸術家たちも親交を持っており、経済的な面での支援とともに芸術推進の協働者として近しい間柄で関わっていました。兄四人、姉三人の八人兄弟の末っ子であったルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)は、このような全方位を世紀末ウィーンの芸術家たちに囲まれた濃密な空気の中で生まれ育ちました。
しかし、彼は華やかな世界にありながらも、特異な苦悩を抱えます。音楽的な才能に溢れた長兄は神童と謳われましたが、父親が自分の経営後継者として期待するあまり自殺をしてしまいます。また、三兄ルドルフもベルリンのパブで服毒自殺します。そして後の第一次世界大戦争従軍中に、次兄クルトは撤退責任によって戦場で自殺しました。残された四男パウルとウィトゲンシュタインも、やはり自殺の衝動に日々駆られていました。また、四男パウルはピアニストとして才能を開かせていましたが、第一次世界大戦争の従軍中に右手を失い、音楽活動に致命的な傷を負いました。ちなみに、モーリス・ラヴェルの「左手のためのピアノ協奏曲」は、このパウルのために作曲されました。
ウィトゲンシュタインはと言えば、そのようなウィーンを代表する芸術家に囲まれていながらも、関心は全く別の方向である機械の構造などに異常な関心を持ちました。この興味は一時のもので終わらず、彼をマンチェスター大学工学研究所の研究生にまで導きます。そこで航空機のプロペラやエンジンの設計に携わり航空工学を学んでいきますが、空へ浮かせる技術に必要な数学へと彼は視点を変えていきます。こうして数学の根本へと関心を移すと、友人からイギリスの数学者バートランド・ラッセルの『数学の原理』を紹介されてのめり込みます。そして数理論理学の礎を築いたゴットロープ・フレーゲに会いにいき、そこからラッセルの元で学ぶ機会を与えられました。ラッセルはアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドとともに『プリンキピア・マテマティカ(数学原理)』を書き上げ、当時において最も注目される数学者でした。この出会いによってもたらされた研究と議論の日々は、ウィトゲンシュタインにとって心身を捧げるほどに熱中し、「数理論理学」や「数学原理」は彼の生き甲斐となって、自殺衝動に駆られ続けた孤独から解放されることになりました。
第一次世界大戦争の規模が大きくなると、ウィトゲンシュタインはオーストリア軍へ志願兵として従軍します。戦場の空気が与える合法的な自殺の誘惑に苛まれながらも、心身ともに耐え抜いた末、そこから生きていこうとする力を得ることになります。生死を懸けた日々でしたが、彼の思考は動きをやめず、「数理論理学」や「数学原理」に対して従軍中も頭を働かせ続けました。閃いた考えや構築した思考を都度書き留めたノートは一つの論考の形となり、『論理哲学論考』の原型が完成します。敗北濃厚となったオーストリア軍は、多くの従軍者を捕虜に囚われていきます。ウィトゲンシュタインはイタリア軍の捕虜となり、コモ、ついでモンテ・カッシーノの捕虜収容所へ移送されました。このとき、赤十字を介してラッセルのもとに送られたのが『論理哲学論考』の原稿でした。母親、そしてラッセルなどの尽力により釈放されたウィトゲンシュタインはウィーンへと戻ります。論理哲学の追究を成しえたと感じていた彼は、論理の研究を継続することはなく、莫大な財産を放棄して、小学校の教師になるべく教員養成所へと通いました。その頃、ラッセルへと届けられた原稿は出版の手筈を進め、紆余曲折はありましたがラッセルの序文を添えた『論理哲学論考』という著作が発表されました。そして、この作品が既存の哲学を根本から揺るがす一大事件として席巻しました。
論理哲学論考
七つの命題
一 世界は成立していることがらの総体である。
二 成立していることがら、すなわち事実とは、諸事態の成立である。
三 事実の論理像が思考である。
四 思考とは有意味な命題である。
五 命題は要素命題の真理関数である。
六 真理関数の一般形式はこうである。
これは命題の一般形式である。
七 語りえぬものについては、沈黙せねばならない。
この論考における最終的な意図は「思想の表現に境界線を定める」ことです。ウィトゲンシュタインは、語りえる事実を論理で提示し、語りえるものの限界を定め、倫理価値や形而上学的存在のような語りえぬものとの限界的境界線を、内側(語りえるもの側)から探究しようと試みました。そして、倫理価値や形而上学的存在は「語りえぬもの」であるため、それらはただ「示されるもの」という結論を導いています。
三・〇三一かつてひとはこう言った。神はすべてを創造しうる。ただ論理法則に反することを除いては、と。──つまり、「非論理的」な世界について、それがどのようであるかなど、われわれには語りえないのである。
ウィトゲンシュタインは、哲学の目的は思考の論理的明晰化であるとして、本質は解明できうるものを解明することであり、哲学的な命題を掲げるのではなく、掲げた命題の不透明で曖昧なものの境界を明確化する活動であると断言しています。命題の本質を提示するということは、論理によって本質を提示することであり、「語りえるもの」を論理によって限界まで提示することであると言えます。つまり、倫理価値や形而上学的存在に至る境界線の内側(これを世界と呼ぶ)を限界まで提示するという行為に繋がります。
世界は論理によって提示でき、世界の限界は論理の限界であるとも言えます。そのため、世界に存在するものを肯定することはできますが、存在の否定あるいは非存在の肯定は為しえません。これらは可能性の排除であり、世界の事実としては認められず、仮に事実であれば論理上の世界の限界を超えることがらと定められます。世界の限界を超えた論理は、いわば倫理価値や形而上学的存在の方面(世界の外側)から眺めることになり、もはや論理ではあり得なくなります。そのような論理上で思考しえぬものは、我々は語りえぬものであるため沈黙せねばなりません。
本書の論考は、過去に生まれた種々様々な哲学がもたらした誤謬や誤認を精査し、今後生み出される哲学に誤解や問題を起こさないようにするという目的が込められめています。古代ギリシャ、古代ローマから受け継がれてきた「論考」の在り方には、各哲学者の願望や憶測が入り混じった記述が多く、倫理価値や形而上学的存在を「世界を語る論考要素」に使用されていたという事実があります。ウィトゲンシュタインはこれを「問題」と捉え、哲学は世界の限界の内側を明晰に語りうるものだけを語る言葉として統一しようとする意思がありました。そして、本論考によって哲学というものの認識統一を図ろうとしました。
ウィトゲンシュタインは、本論考によって世界の限界の内側を明確に定めましたが、彼自身は世界の限界の外側、つまり倫理価値と形而上学的存在にこそ、本論考の意味はあると考えました。「死は生の活動の一部ではなく、生を終えたのちの事実である」という考え方にあるように、「死」のような世界の外側を否定しているわけではありません。「死」を経験することができないことと同様に、世界の外側を語ることはできず、それらはただ我々の前に「示される」のみであるという考え方です。倫理価値においても同様で、倫理自体は「このようにある」と語ることはできず、「このようにあるべきである」というものであり、やはりそれは「示される」ものであると言えます。そしてそれらを論理によって語ること、または命題に取り上げて語ることは、結局のところナンセンスであると考えて、そのように提示しました。つまり、このような「示される」ものは、世界の外側の「神秘」であると受け止める以外に術はないと結論づけています。
ウィトゲンシュタインは、論理を哲学として考えた最初の人間として認識されています。私たちが生きるうえで倫理価値や形而上学的存在の「願望的存在肯定」は、活力の源となり、信仰や善行の重要な要素として心を構築しています。これを、自分の主張を正当化させるために使用した哲学もしくは論理を提示する「誤った哲学者」を正すことこそ、彼の真の狙いであったと思います。
ウィトゲンシュタインは、これらのことが役に立たないと主張しているのではなく、単に言語がそれらを扱うのに適していないと主張しているだけです。たとえば、私たちが世界に対して抱く態度や生き方は、私たちの倫理的な世界観を表現しています。ウィトゲンシュタインは、この世界観が倫理的な格言や法則の形で言葉にされても意味を持ち続けるという考えを批判しています。彼にとって、私たちの倫理的な世界観は示すことしかできず、語ることはできないのです。私たちが哲学とみなすもののほとんどは、語ることができることの限界を超えていると主張することで、ウィトゲンシュタインは哲学の役割を再考しています。哲学は、語ることができることの限界で監視役として立ち、語り表せないことを語ろうとする人々を正すべきです。神の存在、生と死、善と悪、幸福など、人間は生きるために倫理価値や形而上学的存在を必要としています。これらを汚さないように、ウィトゲンシュタインは願っていたのだと感じました。
本書『論理哲学論考』の発表以後、ウィトゲンシュタインは哲学の捉え方を変え、死後に発表された『哲学探究』によって言語論的展開を見せて「後期」の考え方へと移行していきます。しかし、本論考を進めた動機、オーストリア・ハンガリー軍にとって最悪の惨敗と言われる「プルシーロフ攻勢」での苛烈な最前線での退却時に「砲撃のたびに私の存在が縮みあがる。私はもっと生き続けたい。私は時おり動物になる。」という極限の生の体験に見た倫理価値や形而上学的存在を、ウィトゲンシュタイン自身は覆すことはなかったのだと思います。やや難解な論理が散見されますが、必ず心に影響を与えてくれる論考です。未読の方はぜひ、読んでみてください。
では。