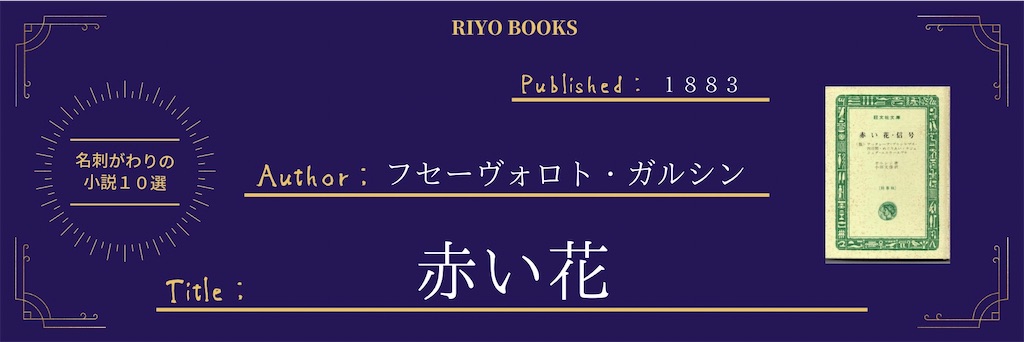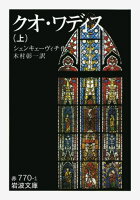こんにちは。RIYOです。
今回の作品はこちらです。

1830年にスティーブンソンが実用化させた蒸気機関車がマンチェスターとリヴァプールを繋いで開通し、イギリス産業革命は成熟期に入ります。機関車や線路の原料である鉄、燃料として使用する石炭、運ぶ売買目的の商業品(紡績、綿織物、工芸品、食品など)は、交通革命の恩恵で莫大な利益と工業地帯への人口増加を呼び起こします。フランシス・ホジソン・バーネット(1849-1924)は、マンチェスターに住む銀装具製造で財を成した裕福な父の元に生まれます。何不自由の無い生活を約束されていましたが、バーネットが僅か三歳の時に父が急死してしまいます。資本主義社会の厳しさに当てられ、瞬く間に貧困の暮らしを余儀なくされました。親戚の元へ身を寄せ、目の前の生活を暮らしていましたが、バーネットにとっては家に備えられていた庭園が遊び相手でした。祖母からもらった花の図鑑を片手に、熱心に植物を観察して大切に育てていきます。父の死と花の生を受けて、生命に関心を芽生えさせていきます。その後、母は兄の助言を受けて、移民を受け入れる新天地アメリカへと子供を連れて渡り、豊かな生活を思い描きます。
1860年に行われたアメリカ大統領選挙で当選した共和党エイブラハム・リンカーンは、公約していた奴隷制度の拡大阻止を改めて掲げました。アメリカ南部諸州では奴隷を用いたプランテーションを中心とした農業が収入源であったため、大きな反発が生まれます。南部諸州は、北部の商業を中心とした生活や環境の違いによって連邦制との整合性を失っていき、遂にはテネシー州を含む旧南部十五州(オールドサウス)が合衆国から分離します。離れた諸州はアメリカ連合国(CSA)という国を立ち上げて、北部のアメリカ合衆国(USA)と真っ向対立します。この激しい戦争は1865年の南部降伏まで続き、アメリカにおいて最も多くの死者を出して終戦します。北部の勝利により公には黒人奴隷は解放されましたが、経済的に自立することが困難な環境であったため、シェアクロッパー(分益小作人)として白人に従い続ける貧困生活を続けました。
南北戦争では軍需によって鉄鋼業、製鉄業を中心とした工業が活性化します。また、スティーブンソンの蒸気機関車技術に感化されるように、サミュエル・モールスの電信技術、タイプライターや輪転機などの商業進化、トーマス・エジソンによる白熱灯や蓄音機の発明などが次々と実用化され、農業大国であったアメリカは巨大な都市国家へと変貌しました。
バーネットは1865年、この国家成長の只中にアメリカのテネシー州へ渡ってきました。しかし国として大きな潤いがあるものの、大衆の多くは貧困に悩まされており、母子家庭であった彼女たちの生活は苦しいものに違いはありませんでした。そこで、飛び抜けた空想力、想像力を持ち合わせていたバーネットは執筆を試みます。僅か十六歳が書け上げたとはとは思えない作品は、家庭の希望となります。出版社もこれを受け入れて、彼女は作家の道を歩み始めました。
しかし数年後の1870年に最愛の母が亡くなります。訪れた悲しみの中でも執筆を続けて作家として成長を続け、徐々に作家として名前が広まり始めます。その悲しみを支えたスワン・バーネットという眼科医と結婚し、二人の子供が生まれました。この次男をモデルとした作品『小公子』を1886年に発表して社会現象となるほどの影響を世に与えます。二年後には『セーラー・クルー』(後に『小公女』と改題して再執筆)を発表し、児童文学作家としての名声を不動のものとします。
幸せはなかなか長続きせず、またも不幸に見舞われます。1890年に長男が病死します。十代半ばの我が子を失った悲しみは深く、家庭内でも不和が起こり始めます。1898年に正式に離婚したバーネットはイギリスへと戻ります。成功を手にした彼女は、ケント州ロルヴェンデンにあるグレイト・メイサム・ホールを住まいとして暮らすことにしました。広大な庭園を持つ美しい建物は1893年に大部分を火災で消失してしまいましたが、住居として利用できる部分は充分残っており、バーネットは改修して移り住みます。この庭で彼女は、蔦に覆われて見つけられない扉をコマドリに教わります。背の高い壁に囲まれた朽ちた薔薇園がそこにあり、僅かな息吹を感じて再び蘇らせようと決意します。まさに本作『秘密の花園』のメアリーが体感したことを、バーネット自身が経験したのでした。このグレイト・メイサム・ホールの庭園は今もなお美しさを保って健在しています。
アメリカでの市民権を1905年に獲得したバーネットはその三年後にニューヨーク州のロング・アイランドにあるプランドームという村に、念願の庭園を備えた家を購入します。丹念に設計された庭園は、彼女の人生の生き甲斐として、伴侶として、最期まで共に過ごしました。
ほとんどいつもひとりきりでしたが、よく知っている花と一緒にいると、決して独りぼっちではありませんでした。ごく自然に、花に話しかけたり、かがみこんでやさしい声をかけたり、キスしたり、友人や愛するものを見るようにその子を見上げる様子がかわいいと褒めたりしました。
『バーネット自伝』
彼女の中で、幼少期に過ごした親戚の家で見た庭園はエデンの園として心の底に染み付いていました。晩年におけるグレイト・メイサム・ホール、プランドームでの日々は彼女に生きる活力を漲らせていました。『秘密の花園』においてもエデンの園を感じさせる描写が数多あります。
朽ちているように見えた樹々を丹念に世話をすると、種々の植物が芽吹き、遂には春がやって来ます。コリンの母リリアス、ディコンの母スーザンは聖母マリアのような面影と心を持って登場人物を優しく包みます。そしてディコンの持つ優しさは自然と言葉を交わし、不思議な暖かい力で触れるものを少しずつ幸福にします。キリストのような印象を持つ彼の聖性を帯びた力は「魔法」と作中で呼ばれています。そして無垢に荒んだ心を持ったメアリーは自然や人々との出会いで心が生まれ変わり、マグダラのマリアの如く美しくなるように描かれています。生命と聖性に溢れた本作の描写は、バーネット自身が庭園を聖的なものとして捉えていたことが窺えます。
しかしながら本作『秘密の花園』は、神の愛や奇跡の物語ではなく、心と心が通う親愛が精神的あるいは肉体的幸福を与え合う物語として描かれています。コリンが自身に起こす奇跡的変化は、「魔法」という自己暗示と、メアリーによるセラピーが起こしています。メアリーは塞ぎ込んでいた彼の心の扉を開き、干渉によって心に変化を与え、交流と衝突で心の在り方に変化を齎します。生きたい、生きようと心の在り方が変化したコリンは望みを唱え続け、自身で「魔法」と解釈した自己暗示による努力を熱心に行い、メアリーは傍らで優しく支え続けます。緩やかな身体的変化はコリンの中で歓喜と感謝で溢れます。明確な神の認識が無い中での神への感謝は、無自覚な信仰として彼の中に現れ、ディコンの教える賛美歌に心が震えます。彼らは神という概念に縋る努力ではなく、親愛による努力と心の在り方を持って彼ら自身を幸福へと導いています。
おら、今までそんな「マホウ」だなんて名前は一度も聞いたことはねえだが、名前なんてどうだっていいだ。おら、ほんとに、フランスでもドイツでも、それぞれちがった名前で、そのことをいってると思うだ。そりゃ、種子をふくらましたり、お日様の光で、おめえ様が丈夫な子になるのと同じ力だから、「いいもの」にちがいねえだよ。
ただ、おめえ様がよろこんでいるかどうかが、かんじんなことだったんだよ。なあ、坊ちゃん、おらたちを楽しくしてくれるえらい方には、名前なんかどうだってかまわねえだ
バーネットの人生には身近な死があまりに多すぎました。生死を見つめる時間は「生命」を考える時間となり、自然との関わり方、心の在り方が与える精神的変化や奇跡的な力を見出しました。晩年になり成熟した思考を持って執筆された本作『秘密の花園』は、読者の心に春を訪れさせる物語と言えます。未読の方はぜひ、読んでみてください。
では。