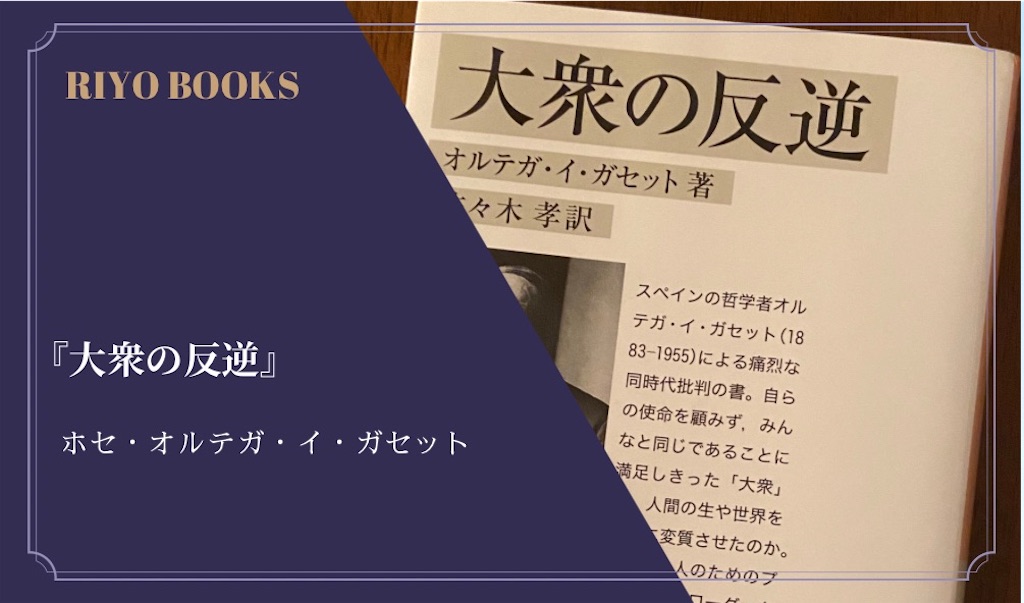
こんにちは。RIYOです。
今回はこちらの作品です。

第一次世界大戦争後、1920年のスペインでは、植民地として支配していたモロッコ北岸の反乱にあい、リーフ戦争が起こっていました。リーフの名家アブデル=クリムが率いる被支配者たちの軍勢は、スペイン軍を打ち破って独立を勝ち取ります。しかし、フランスの将軍フィリップ・ペタンとスペインは手を結び、大軍で攻め寄せてリーフを奪回します。この戦いで大きく名を揚げたのがスペインの将軍フランシスコ・フランコです。スペインではブルボン朝の立憲君主制が行われていましたが、この一連の政治運びに民衆は王政に対して疑問を抱き始め、さらに世界恐慌による経済危機が追い打ちとなり、1931年のスペイン革命によってブルジョワ共和政が成り立ちました。しかし、国内の混乱は収まりを見せず、軍事クーデター、世界恐慌の被害に苦しむ農家、アナーキストたちによる教会襲撃など、矢継ぎ早に問題が起こっていました。この混乱に乗じて右派ファシストの勢力は膨れ上がり、フランコが大規模クーデターを起こしてスペイン内戦を起こします。争いは大きくなり他国を巻き込み始め、ナチス・ドイツのアドルフ・ヒトラー、イタリアのベニート・ムッソリーニがフランコへ手を貸し、スペインを独裁政権へと導きました。
スペインの哲学者ホセ・オルテガ・イ・ガセット(1883-1955)は、幼い頃から秀でた知性を見せて、早くからジャーナリズムの土壌で影響を与えていました。両親と祖父が携わる日刊紙エル・ソルに掲載する形で、混乱する社会に自身の洞察を投げ掛けるように執筆していきます。オルテガは新聞という媒体が最も国民に対して直截的に訴え、集団としての知性に思想を流入できると考えていました。国政の混乱による民衆の戸惑いと、伝統的なヨーロッパ文化圏の民衆が持つべき誇りとの差異に、オルテガは民衆精神の衰退を見て悲観的な態度を示しました。そして民衆意識としてのこの問題を、オルテガは本作『大衆の反逆』によって明確に提示しました。彼は、ボルシェヴィキ独裁やファシズムのような「全体主義」を招く原因は、「大衆」にこそあると主張しています。
オルテガは「大衆」を、「人間としてあるべき行動を示さない人々」と定義しています。この「大衆」は社会的階層には囚われず、政治家や研究者のなかにも含まれるとして、量的表現の「群衆」とは大きく区別しています。いわば人間の精神的区分というもので、その他少数派「エリート」との性質を対比させながら、「大衆」の持つ愚かな危険因子を紐解くように、そしてオルテガ自身の怒りを添えて、ヨーロッパ文化圏に危険を及ぼす恐怖を「大衆による反逆」という表現で紐解いていきます。十九世紀以前では、そもそもヨーロッパ諸国は国家としての境界はあったものの、貴族をはじめとする血の繋がりが国を跨いで入り乱れており、本質的な人間性は各国民を血で繋ぎ止め、共通する矜持や貴族的義務を同じくしていました。このような人間としての性質は国境という区切りを曖昧にして、種族としての共通性でヨーロッパ文化圏を包み込んでいました。オルテガが何度も述べるヨーロッパ文化圏という言葉は、そこに居たはずの「世界を牽引する義務を背負った誇らしい種族精神」を持っていた人間たちによる成果としての文化圏の表現です。このような社会階級に関係なく存在した「立派な精神」の持ち主たちは、現代(1930年出版当時)には見られなくなり、代わりに「大衆」が世に蔓延ってしまったと述べています。
当時の目紛しい産業の発展によって、多くの国民は富、工業、娯楽、情報、安全、医療、権利など、十九世紀では凡そ得られなかったであろう多くの満足を手にしました。しかし、その満足を得たために人間としての「立派な精神」を多く失ってしまいます。工業の恩恵を受けるため、田畑を捨てた農民たちは雇われ人として規律を守る行動を身に付けます。その対価として、人間としての個性を多く失ってしまいました。ヨーロッパ文化圏人としての矜持などは無くなり、領土を区切った国家としての成長へ無自覚に貢献していました。これは国家が推し進めた風潮で、産業の発展に一人でも多くの国民をその成長の「歯車」に組み込もうとした目論見により、ヨーロッパ文化圏人たちが持ち合わせていた「立派な個性」を片端から剥奪したのだと言えます。
そのような「大衆」の性質は、社会に対して悪影響を与えていきます。実際に国家あるいは世界は著しい発展を見せていきますが、そこに住まう大衆の性質は人間的そして精神的に未開のもので且つ、原始的精神らしく欲求に満たされており、計画性も無く社会の流れに身を任せる浮標(ブイ)のような存在であると、オルテガは辛辣に説いています。そして何よりも、政治に与える影響として、他者と同じであることを苦に感じず、またそれを心地良いと捉えるいわば「平均人としての自覚」を抱き、無責任を自由と捉えた価値観によって「平均人としての平等意識」を「真っ当な少数派」へ押し付け、平等への権利は相手が持つべき義務へと変わり、自身の欲求を声高に主張することで、狂乱した不誠実な政治が成り立ってしまうという考え方です。オルテガは思想家の視点から「真っ当ではない権利や主張が罷り通ってしまう」という現実社会を受け止めることができません。ヨーロッパ文化圏が、どのような血の繋がりで、どのような崇高な精神を持って、世界を牽引してきたかという現代に至る歴史を理解せず、満たされた現代に胡座をかいて自らの言動を省みず、好き放題に欲求や権利を主張する平均人たる「大衆」が、芸術の審美眼を持たずに工業の技術的発展に心を躍らせる様を、苦悩的に捉えて説明しています。
つまり私たちは、信じられないほどの能力を有していると感じていても、何を実現すべきかを知らない時代に生きているのだ。あらゆるものを支配しているが、おのれ自身を支配していない時代である。おのれ自身の豊かさの中で途方に暮れている。かつてなかったほどの手段、知識、技術を有していながら、現代世界は、かつてあったどの時代よりも不幸な時代として、あてどもなく漂流している。
そしてオルテガは、あらゆる社会層に存在する「大衆」が一国の支配者に君臨するとき、その野生的エゴイズムによって「真っ当ではない政治主張」を推し進める「独裁」が為されるとして警鐘を鳴らしています。ヨーロッパ文化圏の高貴な精神は潰え、歴史的教養を失った野蛮の精神が、一国を狂乱した不誠実な政治へと塗れさせます。
ヨーロッパならびにその隣接地域でなされつつある政治の「新しい」二つの試み、つまり本質的退行の明らかな二例は、ボルシェビズムとファシズムだ。私がそれらを本質的退行とするのはその教義の内容のためではない。それだけを取り出せばもちろん部分的な真理を持っている──この世界に理性のひとかけらも持たないものがあろうか。彼らの理性を扱う際の反歴史的、時代錯誤的な手法によってそうなのである。大衆化した人間の誰もがそうであるように、凡庸で、間の悪い、昔のことを忘れた、「歴史意識」を持たぬ者たちに率いられた大衆特有の行動は、まるで初めから過ぎ去ったもののように、いまこの時に起こっていながら過去の領域に属しているかのように振る舞うのである。
このような「大衆」によるヨーロッパ文化圏への反逆に対して、オルテガは「優れた少数者」による国家統治を提唱します。自らを律し、自らを省み、自身に国家を前進させる困難や義務を受け止め、真っ当に政治を進めることができる、いわば「エリート」を国家支配者に据える必要があるというものです。ここにオルテガが「選民主義者」と非難された原因がありますが、どちらかと言えば、彼は「失望した理想主義者」であったと言えます。
思想は、真理への王手である。誰であれ思想を持とうと願う人は、真理を欲する姿勢、思想が課す競技の規則を受け入れることがまず必要である。思想や意見を調整する審判、すなわち議論を律する一連の基準が認められないような思想や意見は論外なのだ。これらの基準は文化の原理である。それが何かは重要でない。私が言いたいのは、私たちの隣人が拠るべき市民法の原理がないところに文化は存在しないということだ。討論の際に言及されるような、いくつか究極的な知的立場に対する尊敬の念がないところには文化もない。いざというときに拠りどころとなる商取引が経済関係を統括していないところにも文化はない。美学論争において芸術作品を正当化する必要性を認めないところに、文化はないのだ。以上のことすべてが欠けているところに、文化は存在しない。そこにあるのは、言葉の最も厳密な意味における野蛮(barbarie)である。
多くの面で世界を牽引したヨーロッパ文化圏は、今や「大衆」によってその特性は失われ、新たな進歩を滞らせる危機的状況にあることを、オルテガは危惧しています。真の意味での「貴族意識」、つまり人類という種を牽引しなければならないという義務と自負を自らに課すような「少数者」を生み出す社会を再構築しなければ、愚かな支配者に国を衰退させられ、ヨーロッパ文化圏そのものが崩壊してしまうという恐れを提唱しました。階級社会に対する平等主義は、他者との差異を指摘し合う誤った風潮へと社会を導きました。人間としての意識や能力に差異は必要であり、少数者の持つ突出した能力は、社会や国家を良い進歩へと発展させる原動力となります。この、少数者を平等の権利によって排斥しようとする現象を、オルテガは「モラルの喪失」と表現しています。過去のヨーロッパ文化圏において、高貴な精神を保ち、自らに課題を与えながら乗り越えてきた少数者たちは、見返りなど無くとも義務感(人間はそうあるべきだという思想)で進歩を手助けしてきました。それが現代では、あらゆる階層の人間にモラルが欠如して、野蛮なまでの自己肯定と承認欲求により、文化以上に自分だけを守ろうとしています。この状況を変化させるために、オルテガは「選民主義」のような教育の見直しを提唱しました。平等主義が失わせた文化を、少数者(エリート)たちが再び守り、国民がその利益と保護に感謝を見せ、そのような少数者たちが真っ当に活躍できるような社会を構築することが、何より国家の重要な義務であると訴えました。そして、このような考えを「選民主義」だと反発する精神こそ、当人が「大衆」であるという証明だと言えます。
我々の住む現在の社会でも、モラルの欠如が度々説かれています。しかし反面、必要以上に「平等」を押し付け、高貴な精神や意思を否定する風潮も存在しています。さらに輪をかけるように、資本主義によって強い発言権を持った「大衆」が、野蛮な自己肯定と自己主張を延々と繰り返し、芸術や文化を恐ろしい勢いで衰退させています。まさに「大衆娯楽」に溢れた世界となり、審美眼を持った少数者を排斥しようと躍起になっているようにすら感じます。現在の世界で、芸術や文化をどのようにして守っていくかを、オルテガによる本書によって見直す必要があるのかもしれません。『大衆の反逆』、未読の方はぜひ、読んでみてください。
では。