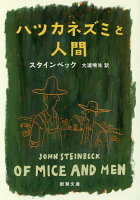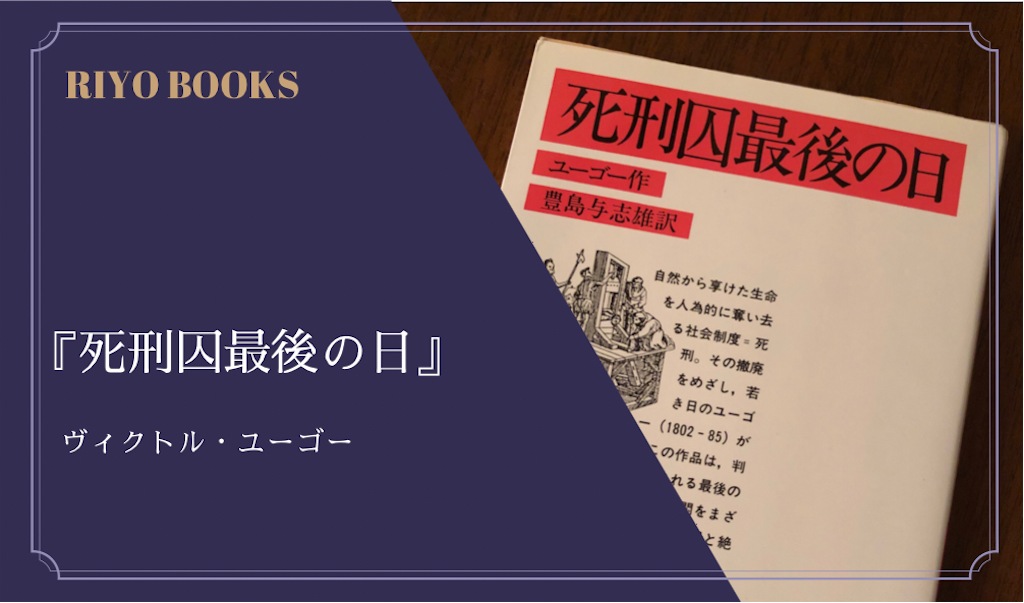こんにちは。RIYOです。
今回の作品はこちらです。
ロシアの国民的詩人アレクサンドル・プーシキンの『スペードの女王』と短篇5作をまとめた『ベールキン物語』です。手元には旧装丁の赤帯がありますので、こちらの紹介文を記載します。
プーシキンが書いたロシア初の小説である『ベールキン物語』。彼は「生命と死」「現実と幻想」の対照的な関係性を融合させた物語を描く「写実的浪漫主義」の人でした。この現実か夢かわからぬ錯覚を覚えさせる世界観は現実以上のリアリズムを感じさせ、生から見た生死を考えさえられます。
また、彼はロシア文学に政治色を強く織り込み始めた一人です。世に対して徐々に文学で先導するようになり「ロシア文学の急進派」、つまりロシア文学の政治に対する意見を強める活動の第一人者となりました。もちろん政府は目をつけ、秘密警察による監視を指示し、自由に作品の発表が出来ない状態に陥りました。彼は十二月党事件(デカブリストの乱)に関わる友人を持っていたことにより、束縛は厳しく保守派の貴族からは疎ましく思われるようになります。この十二月党事件は、農奴制を根源とした「ロシアの後進性」から、自由主義への転換を求めた青年将校たちによる蜂起で、農奴解放を起こす発端となります。
しかしこの段階では、国による物理的、そして精神的な弾圧が圧倒的に強く、十二月党員の首謀者たちは次々に処刑されます。第一次ロシア革命まで80年もの歳月をここから必要としました。
プーシキンはこれらの処遇、あるいは監視にも屈せず「自由な啓蒙」を求め続けます。言論への弾圧に抵抗を続け、ロシア文学の急進を望み文壇活動を継続します。これを嫌った保守派貴族は、彼の妻を巻き込み彼の命を奪う策謀を企てそれを為し、ついにプーシキンの啓蒙活動を止めることになりました。
『スペードの女王』の主人公であるゲルマンにはモデルがあります。十二月党の中心人物の一人であるパーヴェル・ペステリです。農奴制廃止と皇帝専制廃止を強く求めていました。彼も絞首刑により亡くなりました。
ゲルマンは、慇懃で神経質で自尊心の高い人物として描かれています。この人物像は後の巨匠であるドストエフスキーの代表作『罪と罰』の主人公「ラスコーリニコフ」のモデルとなっています。
プーシキンはロシア近代文学の基礎を築きました。批評家のメレシコフスキーは「霊と肉を調和した者」と表現しています。そして、ドストエフスキーは「霊」を、トルストイは「肉」をそれぞれ受け継いだ洞察者としています。
『スペードの女王』は、「生命と死」「現実と幻想」を短篇の中で見事に表現しています。人間の恐怖は加害者にも被害者にも存在し、それらが引き起こす悲劇からも恐怖とわずかな滑稽さが滲み出されています。
『ベールキン物語』は、喜劇も悲劇も文体装飾はさほど無く、リアリズムを軸として人間の情欲の陰陽があっさりと、ですが濃厚に描かれており、読み応えがあります。人物の感情が言動に現れ、当時の階級やしがらみによる苦悩が、くっきりと伝わります。
プーシキンが描いた、当時の貴族的な慇懃さや滑稽さ、可憐さを、新しいロシア文学の進歩として当時発表されたこれらの作品を、ぜひ読んでみてください。
では。