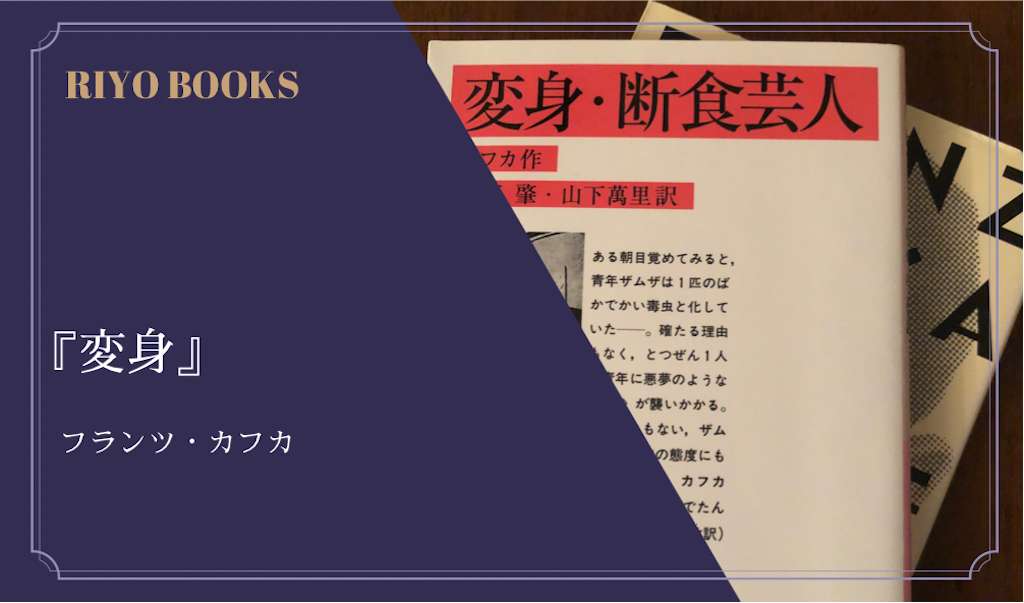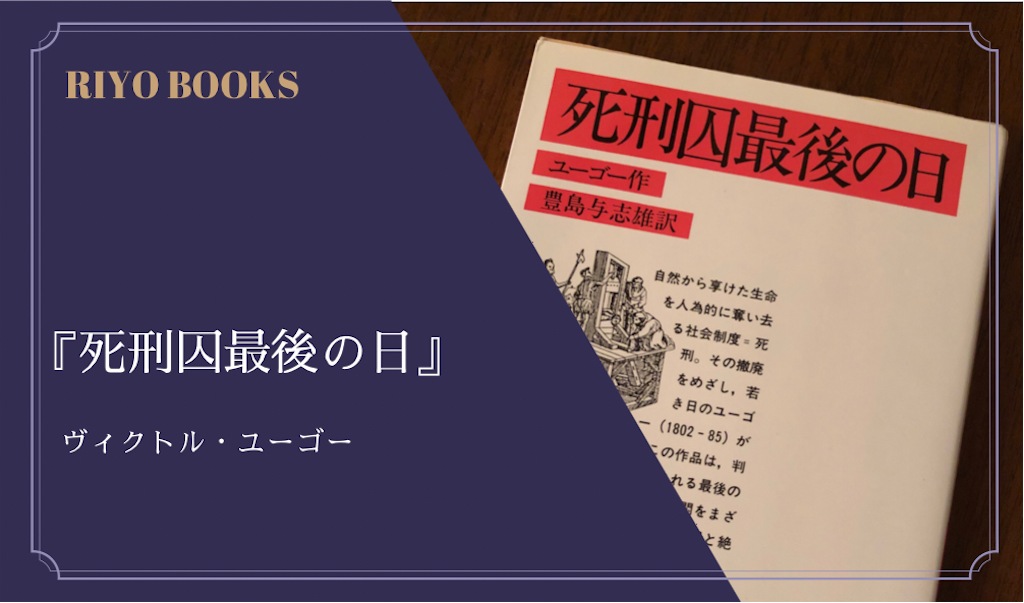
こんにちは。RIYOです。
今回の作品はこちらです。
ヴィクトル・ユーゴー『死刑囚最後の日』です。
フランスのロマン主義第一人者で、『レ・ミゼラブル』を著しています。
1829年に世に出されたこの作品は「著者の名前なし」で出版されました。ノンフィクションかフィクションか、その見極めは読者に委ねるとして冒頭に数行記載されたのみでした。死刑囚が裁判で判決を言い渡され、投獄され、執行されるまでの六週間が描かれています。心理描写の細かさが、刻一刻と迫る執行時間を恐れさせ、心情の生々しい焦燥感を表現するため、読後に手がじっとりするほどの感情移入をさせられます。
人はみな不定期の猶予つきで死刑に処せられている。
判決後は比較的冷静に状況を理解し、「終身懲役より死刑のほうがましだ」とさえ考えていた主人公が、日を追うごとに「生への執着による焦燥」と「死への恐怖」が徐々に、ですがしっかりとした速さで増していきます。ページを捲る手が止まらなくなります。また罪状は明らかにされず、先入観を持つことなく「死刑を待つ心情」に集中して読まされることになります。
ユーゴーは当時ロマン派の詩人として徐々に名声を上げており、フランスにおけるロマンチック運動の先頭に立ち、戯曲でも受け入れられるようになっていました。そして1830年、フランス七月革命においてロマンチック運動の勝利へと導きました。
彼のロマンチシズムは詩・小説・戯曲に盛り込まれ、社会のあり方を世に訴えています。彼は理想主義者でもあります。特に人道的・正義的な側面で熱が高く、この『死刑囚最後の日』は顕著な例と言えます。
その後、1832年に『死刑囚最後の日』の序文を発表しました(こちらも本書に収録されています)。これが政治的・道徳的な見地で大きく議論されることになりました。
彼は人道的正義の人であったので、「死刑制度」を「司法的執行といわれるそれら公の罪悪の一つ」と言い放ち、またこれを目の当たりにする事で大変苦悶しました。
当時の死刑執行は「見世物のようだ」と描写しています。民衆が見やすい席を買い、罪状概要を1スーで売りさばき、婦人達が罪人の乗る馬車を覗き見る。「死刑執行」は誰のための何のためか。そこに苦悩し、死刑制度そのものの撤廃の意思を固めていきます。
社会共同体からすでにその害となりなお将来害となりうる一員を除くことは大事なことだと。--しかしそれだけのことであったら、終身懲役で十分だろう。死が何の役にたつか。
「罰すること」と「処刑すること」は別であり、「処刑」は「社会の復讐」であると述べています。罪を罰するのに「死の意味」がどこにあるのか、強い疑問符で世に問うています。
また併せて、罪を犯す動機の質にも言及しています。
「被告は情熱によって行動したかまたは私欲によって行動したか」
この「情熱による行動」がこの当時における政治犯・思想犯に該当し、この論は七月革命で成った「自由思想」をより活性化させる意図であると見られます。革命前の王政復古により怯えきった民衆の思想を、多く解き放ちたかったのです。
ユーゴーは磔刑台ではなく十字架で罪を罰することができないか、そのように問い、締めくくっています。
死刑の不道徳性や不要性を、当時の社会と照らし出したこの作品。一気に読み進んでしまう筆致をぜひ体感してください。
では。