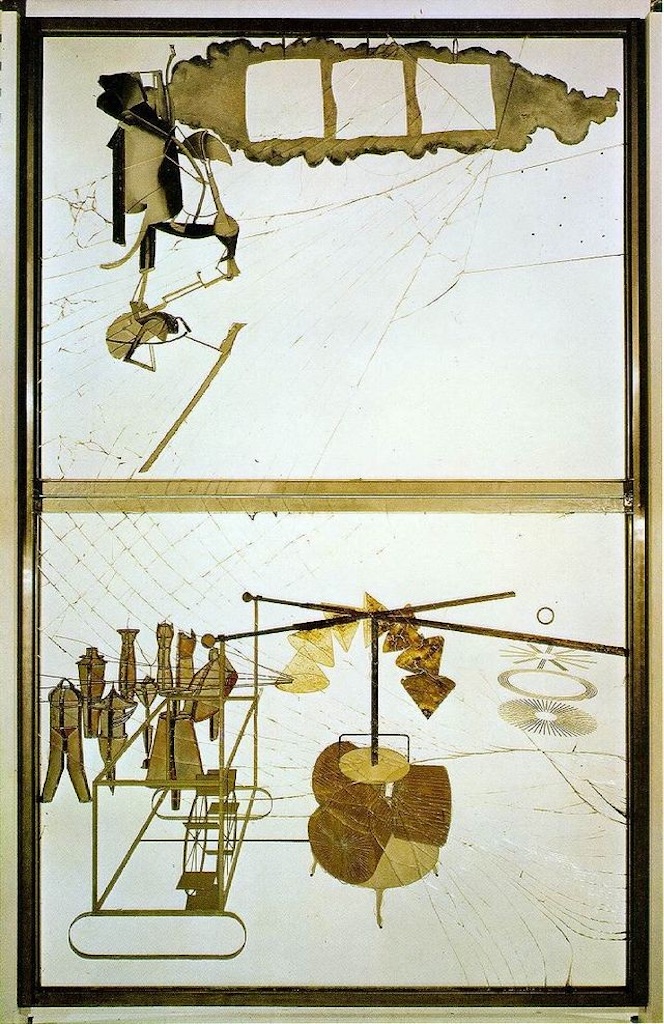こんにちは。RIYOです。
今回はこちらの作品です。
アレクサンドル・デュマ・フィス(1824-1895)は、私生児として生を受けました。父はアレクサンドル・デュマ・ペール。『三銃士』『モンテ・クリスト伯』『王妃マルゴ』などを執筆した文豪です。この通称「大デュマ」とされる父は、将軍の息子として生まれます。
奴隷の子から成り上がったこの将軍は、ナポレオン・ボナパルトと共に遠征するほどに活躍しましたが、ナポレオンの遠征を批判したために関係が悪化。遠征先からフランスへ帰国させられます。関係回復が見込めない中で文豪大デュマは生まれました。貧しいわけではありませんでしたが、将軍は散財し、財産を殆ど残すことなく大デュマが四歳のときに亡くなります。苦しい学生生活を経たのち、大デュマは上流階級の人脈により、後のフランス王ルイ=フィリップ一世の秘書として収まることになりました。生活が安定してきたころ、下着の縫製業を営む女性を誘い、子供を産ませます。これが「小デュマ」こと、デュマ・フィスです。私生児は彼だけでなく、数人いたと言われます。
元々、大デュマは劇作家を目指しており、その活動は大変に熱心で多数の戯曲や散文を生み出します。当時はシェイクスピアを中心としたイギリス演劇が主に演じられていましたが、若い世代でロマン派の動きが見え始めたころでした。大デュマはこの風潮に属し、ロマン主義演劇作家のひとりとなり、傑作を生み出していきます。
デュマ・フィスは七歳のときに大デュマに認知され、金銭面での援助を存分に受けて満足な教育を受けることとなります。しかし家庭的な愛には恵まれず、母と引き離されて育ち、徐々に心が擦れていきます。父の援助金を遊びに遣い、大デュマを思わせるような放蕩ぶりを見せます。ここには、家族愛の欠如だけではなく、それによる社会の偏見、生きづらさなどが含まれていました。浪費する額が存分にあったため、クルチザンヌ(高級娼婦)とも交遊が始まります。そして出逢ったひとり、マリー・デュプレシと恋に落ちます。彼女こそ本作『椿姫』のヒロインであるマルグリットのモデルとなっています。
さて、この物語は事実あったことで、登場人物も、女主人公のほかはみんな、今なお生存しているということを、まず読者諸君に信じていただきたいと思う。
冒頭にこの社会が事実であったことを強調されています。しかし実際はノンフィクションではありません。中心となる貴族の息子のモデルには父親はありませんでしたし、デュプレシはクルチザンヌの生業から抜け出すことはありませんでした。
デュプレシの生い立ちは貧しく、行商人の娘として幼い頃より春を売ることを強要されました。彼女は大変美しい外見を持っていたために、話題にされ名が広まっていきます。やがて貴族の耳にも入り、その美貌で魅了して囲われ始めます。そこで読書やマナーを躾けられ社交界デビューしました。ここからクルチザンヌとして生きていきます。
彼女は日々、劇場へと足を運びます。劇場は当時、出逢いの場、或いは密会の場として使われていました。桟敷に着くと、腰を据えてお客の訪問を待ちます。彼女が求めている時、桟敷に「白い椿」を飾っていました。営業中の知らせとして、そしてそうでない時は「赤い椿」を飾ります。月に約五日間は赤い椿が飾られ、ただ出逢いだけを求めていることを知らせていました。
クルチザンヌだけでなく、フランス全体の国民病として肺結核が猛威を奮っていました。デュプレシも例に漏れず、肺を病んでいました。しかし安静にすることはさほどなく、苦しみながらもそれを見せず、死の間際まで白い椿を飾り続けました。享年は二十三歳でした。
彼女に魅了された後世に名を残す偉人はデュマ・フィスだけではありません。「リゴレット」「アイーダ」などを代表作とする偉大なオペラ王、ジュゼッペ・ヴェルディです。そして彼はデュマ・フィスの小説を元にして書いた戯曲を、美しいオペラ「椿姫」として作り上げます。今なお愛され続ける傑作です。小説に比べて愛の物語の色が強く普遍性を持っていることが、全世界で受け入れられ続ける理由のひとつとして考えられます。
デュマ・フィスの『椿姫』は強く社会を写実的に描いています。描かれる苦悩をより多く感じさせられます。『椿姫』は貴族の息子とクルチザンヌによる愛の物語です。しかし、背景にある「社会悪」「道徳」「正義」を物語に乗せて、社会に訴えるように描かれています。何よりも「父権制社会」の苦悩は、角度を様々に変えて非難しています。自らの生い立ちである私生児が抱く苦悩、女性の社会的立場に対する苦悩、貧困が奪う夢に対する苦悩など。貴族社会と同義的に感じられる点も、必ず「父権制」が滲むように描写されています。社会そのものを出来る限り作品に閉じ込め、これを悲劇で締め括ることによって、社会そのものへの批判、つまり父権制社会への糾弾として描きました。
あなたはアルマンを愛していてくださる。それならばそれで、その証拠を伜に見せてやっていただきたい。その証拠を見せる方法は、まだ一つだけあなたに残されている。それは伜の将来のために、あなたの恋を犠牲にすることです。今までのところべつになんの不幸も起こってはいないが、しかしいずれは起こるようなことになる。しかもそれは、わたしの予想するよりもさらに大きな不幸であるかもしれん。
貴族の息子であるアルマン、その父親がマルグリットへ優しく説く場面での台詞です。恐らくこの父親は大変寛大で心根の優しい実直な人柄であると受け取ることができます。しかし、その会話の中で「当然とされる社会の風潮」は非常に父権性を帯びています。一度蔑視されたものは、二度と清らかな存在となり得ない。どのように心を入れ替え、行動を慎んだとしても、世間に根付いた価値が覆ることはない。あなたは生涯クルチザンヌなのだ、ということをとても優しく諭し、またマリエットも感謝して受け入れます。物語を追って得る感動は、読み終えると苦悩と切なさに変わります。
語り手は、清新に昇華した女性としてマルグリットに敬意を払います。しかし、それが亡くなってから、もとい亡くなったからこそ払うことができる敬意というものは物悲しく感じさせられます。
マルグリットの心、生き方を変えたのは「初めて触れた真心」でした。純粋な優しい心に幼少期から触れることができていれば、クルチザンヌとして生きることはなかったのかもしれません。
美しくも切ない愛の物語。非常に読みやすく、時代背景を感じやすい文体となっています。
未読の方はぜひ。
では。